2025年8月9日、チヌ釣りの釣果

クロダイ44㎝、43㎝、42㎝×2、41㎝、40オーバー5尾。
加えて、クロダイ38~30㎝、16尾。計21尾。
最近、イマイチの釣果が多かったので、悩んでいたけど、
この日、ちょっと挽回できて、ひと安心。
次回は、更に上を目指します。
釣行前のチェック
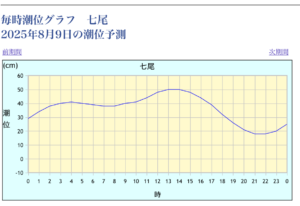
潮周りは、大潮。
7時25分、干潮。13時36分、満潮。
大潮の割には、釣りの時間は、潮位変化は小さい。
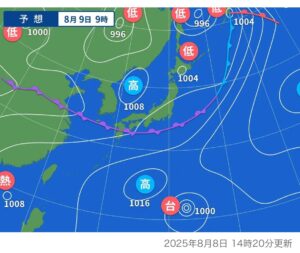
予想天気図は、高気圧。
太平洋側に前線があるけど、影響はなさそう。


最高気温は、30℃で、しのぎやすそう。
風は、西風2.5m。
なので、ボート釣りで、ラスト15時まで粘れそうかも。
この日のチヌ釣り作戦
先週は、カセ釣りの島田さんで、クロダイ39㎝~33㎝計9尾。
毎年この時期、ネリエのウキフカセで、それなりに釣っていたはずなのに、
今年は、なぜか低迷中。
なぜ釣れないのか?改めて考え直して、この日の作戦は、以下の通り。
- 牡蠣貝が、たっぷり付いた沈みウキ玉狙いのボートランガン
- たっぷりマキエをして、マキエとネリエを同調させる
- 牡蠣貝際狙いの時には、エサ取りがいるので、ネリエをケチらないで大きく付ける
牡蠣貝が、たっぷり付いた沈みウキ玉狙いのボートランガン
牡蠣棚のチヌ釣りで、狙い目は、①アンカーの着地点、②牡蠣貝がたっぷり付いた沈みウキ玉、が考えられる。
アンカーの着地点とは、アンカーロープが海底に固定されている場所で、漁礁になっている。
牡蠣貝がたっぷり付いた沈みウキ玉とは、牡蠣棚の牡蠣貝が生育して大きくなると、重くなって、ウキ玉が沈んでいく。裏を返せば、沈みウキ玉の場所は、付いている牡蠣貝が大きい。更に、そこには色々な生物が付着している。
この時期、クロダイは、アンカーの着地点よりも、牡蠣貝がたっぷり付いた沈みウキ玉の方が、エサが豊富なので、その付近に生息していると推測。
牡蠣貝がたっぷり付いた沈みウキ玉を、どんどんボートランガンして探っていく作戦。
たっぷりマキエをして、マキエとネリエを同調させる
先週の釣りを振り返ると
1.先ず、マキエをまかないでネリエ投入。
2.釣れなければ、マキエをして、ネリエ投入。
結果は、マキエなしでは、チヌが全く釣れず、アタリすらなかった。
でも、そのあとにマキエをまくと、ネリエの落とし方は、同じでも、今度は、チヌが釣れた。
このことから、例え、ネリエの落とし方が下手くそでも、マキエをまけば、チヌが釣れる。
そう仮説を立てた。
おそらく、普段は警戒心が強いチヌでも、一旦、マキエを食いだすと、警戒心が弱くなってしまう。
普段は、牡蠣貝の際を、ごく自然に落ちてくるものにしか反応しないチヌでも、
一旦、マキエを食いだすと、多少、牡蠣貝から離れていても、あるいは、多少、不自然に落ちてきたとしても、チヌは食ってしまう。
なので、たっぷりマキエをして、マキエとネリエを同調させて、チヌの警戒心を弱くして、ネリエを食わせる作戦。
牡蠣貝際狙いの時には、エサ取りがいるので、ネリエをケチらないで大きく付ける
この時期、牡蠣貝の際には、エサ取りが多くなってきた。狙い目が、牡蠣貝がたっぷり付いた沈みウキ玉なので、なおさらだ。
普通に、鈎にネリエを付けて落とし込んでも、チヌのタナに届く前に瞬殺されてしまう。
そこで、鈎にネリエを大きく付けて、エサ取りが多少かじっても、その下層にいるチヌに届くようにしないといけない。
なので、牡蠣貝際狙いの時には、エサ取りがいるので、ネリエをケチらないで大きく付ける作戦。
そもそも自分のチヌ釣りは、マキエを使ったウキフカセ。
今一度、その原点に戻って、最近、苦戦していた夏チヌの攻略に再挑戦だ!
クロダイ釣りの記録
エサ

マキエは、15時まで粘るつもりで多め、
アミ2角、オキアミ2k、チヌベスト2袋、チヌパワームギスペシャル2袋。
サシエは、ネリエ、食い渋りイエロー3袋と高集魚レッド3袋。
ネリエはケチらないで、多めに持ってきた。
タックル

竿は、がま磯アテンダー3 1‐50。
リールは、シマノスコーピオンDC。
道糸は、サンヨーナイロンアプロードディテール2.75号。
ハリスは、シーガーグランドマックス1.75号。
ウキは、グレックスダンガンチヌ00号。
深いタナを探らないので、000号でなく00号に。
鈎は、がまかつチヌ5号か3号。
使い分けは、チヌの活性が高い時は、飲み込まれやすい。そうなると面倒くさいので5号に。
逆に、活性が低い時は、食い込みやすくするために、鈎を小さく3号に。
海水温

海面の水温は、28℃。
雨の影響で水温が少し下がったようだ。
チヌの食いはどうだろうか。
実釣レポート

5時27分、出港。


5時57分、ポイント到着。
ツインブリッジから4列目の、ウキ玉が沈み気味の場所。

海釣図Vでは、こんな感じ。

6時16分、マキエ開始。

6時41分、ネリエをマーブルにして1投目。

6時43分、クロダイ36㎝。

6時56分、クロダイ36㎝。

7時1分、クロダイ33㎝。

7時6分、チンタ。

7時11分、クロダイ30㎝。

7時32分、クロダイ35㎝。

7時36分、クロダイ37㎝。

7時46分、クロダイ34㎝。

8時4分、クロダイ38㎝。

8時19分、チンタ。

8時22分、場所移動します。


8時31分、2番目のポイント。
牡蠣貝がたっぷりの場所。
最初のポイントから少し沖に出た。

海釣図Vでは、こんな感じ。

8時48分、チンタ。
この後、アタリがあったがラインが切られた。
よく見ると、ハリスがボロボロ。
上からじゃ見えないけど、海中にはロープがあちこちにあるようだ。
ここでは釣りができない。
なので、ちょっと移動。

9時19分、クロダイ44㎝。
牡蠣貝の際で食わせた会心の1尾。

9時25分、チンタ。

9時42分、チンタ。

9時43分、場所移動。


9時53分、1番目のポイントの向かい側。
ウキ玉が沈んでいて、牡蠣貝が、たっぷり付いていそう。

海釣図Vでは、こんな感じ。

10時14分、後半マキエ開始。

10時25分、クロダイ30㎝。

10時34分、クロダイ33㎝。

10時40分、クロダイ41㎝。

10時56分、クロダイ32㎝。

11時5分、クロダイ43㎝。

11時32分、29㎝なのでチンタ判定。

11時37分、クロダイ37㎝。

11時46分、クロダイ30㎝。

11時54分、サイズダウンしてきたので、少し移動。

12時17分、場所移動。


12時24分、4番目のポイントは、平行移動した場所。

海釣図Vでは、こんな場所。

12時42分、29㎝のチンタ。

12時48分、チンタ。

13時12分、クロダイ34㎝。

13時18分、クロダイ31㎝。

13時25分、場所移動。


13時32分、5番目の場所は、ツインブリッジから3列目手前。
やはり牡蠣貝がびっしりついて、ウキ玉が沈み気味。

13時58分、クロダイ42cm。

14時5分、クロダイ42cm。
40オーバー連発。

14時13分、クロダイ30cm。

14時40分、納竿。
クロダイ40オーバー5尾、計21尾。
ランガンして、デカいチヌの居場所に入れて、ラッキーでした。
ただ、相変わらず、牡蠣貝に突っ込まれてのバラシなど、課題山積。
その課題を解決して、次回は、年無クロダイが釣りたいです。
この日のチヌ釣りの振り返り
向う側の牡蠣貝際の攻略法
この日、向う側の牡蠣貝際を狙って、いろいろ試行錯誤して、
以下の方法で攻略できたので、ご紹介します。
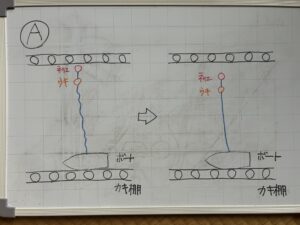
図Aは、向う側の牡蠣貝の際を狙っている様子です。
普通に、向う側の牡蠣棚に仕掛けを投入すると、仮に、ネリエを丁度、牡蠣貝の際ギリギリに投入できたとしても、ラインのたるみを巻き取ると、結局、ネリエが牡蠣貝から離れてしまいます。
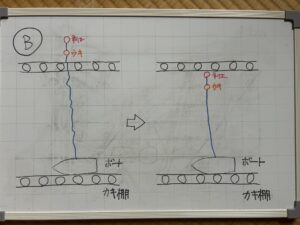
で、いろいろ試行錯誤した結果、図Bのやり方で、割と簡単に上手くいきました。
先ずは、向う側の牡蠣棚の更に向う側まで投げてしまう。
そして、すぐに、巻き取って、ネリエが丁度、牡蠣貝の際ギリギリのところで巻き取るのを止める。
仕掛け投入時は、向う側の牡蠣棚に仕掛けを引っかけないように、コントロール良く、投入する必要があるし、またネリエが沈まないうちに、牡蠣貝の際ギリギリのところまで、素早く巻き取ってくる必要があります。
もちろん、潮流が、向う側の牡蠣棚に向かって流れていると、より牡蠣貝の際に落とし込みやすいです。
また、この日、足元の牡蠣貝の際、向う側の牡蠣貝の際、両方を狙いましたが、向う側の牡蠣貝の際の方が、スレにくいように感じました。
ここでチヌ釣りをしていて感じるのは、あるポイントに入って、1尾目には割と大きいのが釣れる。でも、更に、2尾、3尾と釣るにしたがって、だんだんサイズダウンしていく。これは、だんだん、そのポイントがスレてくるように思っています。
鈎に掛かったチヌが暴れるから、ほかのチヌが警戒心を持つのかもしれません。
また、人間の気配を感じて、ほかのチヌが警戒心を持つのかもしれません。
実は、自分はボートのランガンで、あちこち移動するのは、このスレを感じるからなのです。
もし、向う側の牡蠣貝の際を、もう少し攻略できるようになれば、移動を少なくできるかもしれません。
そうなれば、もっと数釣りができるかも。
バラシ対策
この日、相変わらず、足元の牡蠣貝に突っ込まれて、ハリス切れのバラシがあった。
向う側の牡蠣貝に突っ込まれても、割と簡単に取れる。
でも、足元の牡蠣貝に突っ込まれると、ハリスを切られることが多い。
5mの磯竿を使っているのに、何でこうなるのか?
理由は、ハリスが長いから(通常2ヒロ=3.2m)。
ハリスの上にウキが付いているので、リールを巻きとっても、ウキまでしか巻き取れない。
すなわち、3.2m分、遊びがあって、その分、鈎にかかったチヌが、足元の牡蠣貝に接触できる自由度があるということ。
では、どうするべきか?
ハリスを短くすること。
自分は、もともとは磯釣りがメインだったので、ハリス2ヒロが当たり前だった。なので、牡蠣棚で釣りをするようになっても、何の疑いもなく、ハリス2ヒロを当たり前にしていた。
そのハリス2ヒロを、次回は、1.5ヒロにするつもり。
ハリスを短くして、チヌの食いに、どう影響するか、確認する必要がある。
遠矢ウキの遠矢さんは、ハリス1.5ヒロでも、チヌをバンバン釣っているので、おそらく問題はないと思う。
まだまだ未熟。
もっと勉強しなければ。



コメント